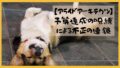株式会社ACCESSの米国子会社IPI社は、2022年3月からドイツのAa社にネットワーク機器向けソフトウェア「OcNOS」のライセンスとメンテナンスサービスを提供しており、2024年1月期に売上は大幅増加しましたが、売掛金の回収期間が長期化しました。
2024年7月末時点でAa社向け売掛金約35百万ドルが計上され、監査法人の指摘により約2百万ドルの貸倒引当金を計上しました。
回収遅延の原因調査のため10月に社内調査委員会を設置したところ、Aa社との取引に加え、台湾のAb社との2020年の10百万ドルのpre-buy取引についても不適切な売上計上の疑義が発生しました。
より専門的で客観的な調査のため、11月29日に外部専門家による特別調査委員会を設置し、調査を実施することを決定しました。
この記事では、ACCESSが公表した調査委員会の調査報告書に記載されている不正の内容、発生原因に焦点を当てて要約しています。
※詳細は株式会社ACCESS特別調査委員会「調査報告書」(PDF)をご確認ください。
会社概要
株式会社ACCESS
- 資本金:17,072百万(2024年1月31日時点)
- 連結売上高:16,573百万円(2024年1月期)
- 従業員数:809名(連結)
- 事業内容:IoT事業、webプラットフォーム事業、ネットワーク事業
コーポレートガバナンス体制
- 取締役会:社内取締役3名と社外取締役5名で構成され、、毎月1回の頻度で定時取締役会が開催
- 監査役会:監査役3名(3名とも社外監査役)で構成され、うち2名が常勤監査役
IPI社
- 資本金:115百万ドル
- 売上高:9,235百万円(2023年12月期)
- 従業員数:389 名
- 事業内容:ネットワーク事業
IPI社の管理状況
ACCESSは、各事業セグメントの業績管理と事業連携のため、子会社役員との兼任を実施しており、取締役のXb氏またはXd氏がIPI社の会長を兼任しています。
2018年10月以降、IPI社の取締役会はXc氏、Xb氏、Xd氏の3名体制となっており、Xc氏は2020年4月からACCESSの執行役員を兼任し、2024年4月から常務執行役員を務めています。
グループ会社の全般的な管理は、関係会社管理規程に基づき経営企画部が主管として実施し、各管理部門が各グループ会社の担当者と連携しています。
業績モニタリングでは、経営企画部と経理部の協力の下、各子会社から月次報告パッケージを受け、集計結果をOverseas Board MeetingやIPI社取締役会、ACCESS取締役会等で報告しています。
内部監査については、海外子会社は基本的に3年に1回程度実施しており、2020年はコロナ影響で未実施、2021年はリモート監査を実施しました。2017年以降、IPI社及びその子会社に対して複数回の監査を実施しています。
監査役監査では、2020年1月期に海外グループ会社の往査実施が指摘され、その後はグローバルなリスク対応の観点から子会社等の内部統制及び本社の関係会社管理状況に留意する方針が示されています。
IPI社への監査は経営会議等での報告聴取や担当役職員への事情聴取等を通じて実施され、特段の指摘事項は報告されていません。
調査の結果判明した事実
概要
この調査では、「ライセンス取引」及び「pre-buy取引」以外にも複数の会計上の疑義が検出されました。
そのため、あずさ監査法人と連携して情報を相互に共有し、一定の量的・質的重要性を有する事案を特別調査委員会の調査対象とし、その他の事案は監査対応の中でACCESS及び外部専門家が検討するという役割分担を基本的な調査アプローチとしました。
特別調査委員会は、類似事案として、以下の事案を調査対象に含めました。
- 「返金条件付取引」:2017年のIPI社とAc社間のOcNOSライセンス取引
- 「バーター取引」:2018年のIPI社とインド企業Ad社間のOcNOSソースコードライセンス取引及び業務委託取引
- 「buy-out取引」:2019年にACCESSグループ傘下となったNetRange社とAg社間のポータルサイトライセンスbuy-out取引
- 「ソフトウェア資産化」:IPI社におけるソフトウェア開発費用の不適切な資産化疑義
一方、ACCESSはこれらの調査と並行して、あずさ監査法人と協議しつつ外部専門家の支援を受けながら過年度の会計処理を再検討しました。
特別調査委員会は再検討対象について独自調査は行いませんでしたが、定期的な情報共有を受け、必要な範囲で調査により得た情報を提供しました。
この再検討の結果、ACCESSは調査対象事案以外に合計27案件について過年度の会計処理訂正が必要と判断しています。
ACCESS及びネットワーク事業の事業環境
ACCESSは1998年に携帯電話向けブラウザを開発し、2008年には売上高300億円を超える規模まで成長しましたが、2017年1月期には約66億円まで縮小しました。同社はIPI社が開発したネットワークOS「OcNOS」に期待をかけ、ネットワーク事業を次の成長ドライバーとして位置付けました。
2018年1月期から2025年1月期までの予算と実績を見ると、IPI社は継続的に予算未達となっており、特に2021年1月期には売上予算47億円に対して実績18億円と大幅な未達でした。ACCESSは期待する成果を得るため、IPI社に対して継続的な投融資を実施し、総額で数十億円規模の資金投入を行いました。
事業環境の変化として、新型コロナウイルス感染症の影響、東証市場変更の取り組み、大株主Al社からの厳しい指摘、Ak社との資本業務提携などが挙げられますが、期待された成果は得られず、慢性的な赤字状態が続きました。
返金条件付取引
IPI社は2017年12月、At社との間でOcNOSソフトウェアのライセンス契約を1百万ドルで締結し、全額を売上計上しました。しかし、契約交渉段階で既にAt社への1百万ドル返金が合意されており、実質的には返金条件付きの取引でした。
問題の構造
At社は本来OcNOSライセンスを求めておらず、IPI社への投資や資金提供を目的としていました。しかし、IPI社のXc氏が2018年1月期に収益認識を行うため、ライセンス取引の形式を取りました。
返金条件については、監査対策として別途Strategic Alliance Agreementに記載し、監査人には開示されませんでした。
実際の資金移動
2018年から2019年にかけて、両社間で複雑な支払いが行われましたが、最終的に2019年3月にライセンスが「キャンセル」され、全額が精算されました。この間、監査対策として虚偽の請求書や説明文書が作成されていました。
会計処理の問題
収益認識の要件である「回収可能性の合理的保証」を満たしておらず、売上計上は不適切でした。正しくは仮受金または仮払金として処理すべきでした。
バーター取引
IPI社は、OcNOSのソースコードライセンスを6百万ドルでAd社に付与する契約(LA契約)と、8.7百万ドルでOcNOS開発業務等をAd社に委託する契約(SOW契約)を同日付で締結しました。
調査の結果、以下の重大な問題が明らかになりました。
契約内容の不備:
LA契約では、ソースコードのバージョン、利用可能地域、対象ハードウェア製品などの重要な詳細が未定のまま契約が締結されており、これらの詳細を決める議論も行われていませんでした。
価格設定の不自然さ:
ソースコードの対価は交渉過程で1百万ドルから6百万ドルまで大きく変動しましたが、ライセンス内容や機能に基づく検討ではなく、専らSOW契約との関係で決定されていました。
実質的な目的:
取引開始時から「Ad社から売上を上げること」が主目的とされ、Ad社のソースコード活用ニーズは考慮されていませんでした。実際、Ad社はソースコードを活用した製品販売を行っていません。
特別調査委員会は、SOW契約の対価8.7百万ドルのうち6百万ドルが水増しされており、LA契約の売上6百万ドルを取り消し、SOW契約の原価から6百万ドルを減額する会計処理の訂正が必要と判断しました。
buy-out取引
ACCESSの子会社NetRange社は、2019年12月31日付でAg社との間で、スマートテレビ用ポータルサイトのライセンスを200万ドルでbuy-outする契約(MoU修正契約)を締結したとして、同期の収益として認識しました。
しかし実際には、契約交渉は2020年2月まで継続しており、契約締結日がバックデートされていました。
調査の結果、以下の問題が明らかになりました。
契約締結時期の偽装:
実際の合意は2020年2月であったにも関わらず、2019年12月31日締結として処理していました。
サイドレターの隠蔽:
Ag社がLong Form Agreement(LFA)の締結まで支払いの大部分を留保できる権利を定めたサイドレターが存在したが、これを監査法人や経理部門に開示していませんでした。
収益認識基準違反:
IFRS15に基づく契約識別要件を満たしていない状況で収益を認識していました。
国際財務報告基準(IFRS15)に基づく適切な会計処理では、収益認識時点を2020年7月21日(LFA締結時)とすべきであり、NetRange社2020年12月期に計上されるべきでした。これは意図的な収益の前倒し計上による不適切な会計処理と認定されます。
pre-buy取引
IPI社は2019年12月、Ab社に対してVyattaとOcNOSのソフトウェアライセンス(合計10百万ドル)を販売し、同年12月期にその全額を売上計上しました。
しかし、この取引には以下の問題があるため、形式的な契約書面と経済実態の乖離により、不適切な収益認識が行われた典型例といえます。
リスク低減策の存在
Ab社のリスクを軽減するため、IPI社は複数の対策を講じました。
- 2020年3月1日付でMarketing Agreementを締結
- バンドルソリューションの売上が2年間で目標売上23百万ドルに満たない場合、IPI社が最低でも目標売上未達額の半額をAb社に支払うことを約束
- 10百万ドルの未回収分に対する利息を四半期ごとに支払う合意
契約の結合による会計上の問題
ライセンス契約とMarketing Agreementは実質的に同時期に合意されており、ASC606の契約結合要件を満たします。これにより、Ab社は本件ソフトウェアに係る重要なリスクを実質的に負担していないと評価されます。
収益認識の適切性
Marketing Agreementの補償条項により、Ab社のソフトウェアリスクが実質的にゼロとなっているため、2019年12月31日時点での収益認識は不適切でした。適切な収益認識時期は、Ab社が直接外部顧客に販売した時点、またはIPI社が買戻しを行った時点となります。
必要な会計処理の訂正
- 契約負債として処理すべき
- Marketing Expenseは利息費用として認識
- 実際の販売・買戻し時に収益認識
ライセンス取引
IPI社は2022年3月以降、Aa社との間でOcNOSソフトウェアのライセンス取引を開始し、2022年から2024年にかけて約6,500万ドルの売上を計上しました。Aa社はIPI社にとって最大の取引先となりましたが、この取引には重大な問題が複数発見されています。
取引当事者の実態不明
Aa社は2021年8月にドイツで設立された企業ですが、実態が極めて不透明です。登記住所は集合住宅の一室で、郵便受けには別会社名が記載されており、Aa社の社名は確認できませんでした。
また、交渉窓口であったXa氏とAa社代表者Yl氏の関係性も不明確で、IPI社内では長らく同一人物と認識されていました。
不適切な売上計上
多数の取引において、売上計上日よりもアクティベーションコード送付日や適合バージョンのリリース日が大幅に遅れています。
特に問題なのは「ダミーシップメント」と呼ばれる手法で、実際には使用可能でない製品を形式的に出荷して売上を計上していたことです。報告書作成時点でも未リリースの製品が存在します。
第三者経由の支払い
2022年12月頃から、Aa社からの直接支払いが滞り、香港等に所在する第三者企業からの送金に変更されました。2024年9月時点で約1,900万ドルが3ヶ月以上の滞留債権となり、貸倒引当金も計上されています。これらの第三者弁済の法的有効性には疑問が残ります。
ロシア企業との関連
当初、IPI社はロシア企業のAy社とも契約を検討していましたが、ウクライナ侵攻を受けてリスク回避のためAa社との契約に一本化した経緯があります。しかし、Xa氏は元々Ay社の代表であり、両社の関係性は不透明です。
調査委員会は、US-GAAPのASC606(収益認識基準)に照らして、多数の取引で売上計上時期が不適切であったと結論づけています。
履行義務が充足されていない時点での売上計上や、ダミーシップメントによる人為的な売上計上は会計基準に違反しており、売上計上時期の修正や一部取引の売上取り消しが必要としています。
また、M&S(保守サポート)についても、対応するソフトウェアの売上計上後に開始されるべきところ、不適切な計上が行われていたとして修正が必要と判断しています。
ソフトウェア資産化
IPI社では、OcNOSを中心とするソフトウェア開発費の資産計上において、大きく3つの不正行為が行われていました。
費用から資産への不適切な振替処理
2015年から開始されたソフトウェア開発費の資産計上比率が、年度により25%から93%と極端に変動していました。Xe氏の指示により、Finance部門担当者が本来費用として計上すべき作業時間を資産項目に振り替えていました。
具体的には、「研究開発における日常的顧客対応活動」や「全顧客サポート」といった、本来資産化できない性質の費用も資産として計上されていました。
技術的実現可能性達成時点の前倒し
米国会計基準では、技術的実現可能性が達成された時点から開発費を資産計上できますが、OcNOSの一部バージョンについて、Xe氏の指示により本来の達成時点より早い時点で達成されたものとして扱われ、資産計上時期が早められていました。
監査人への証憑改変
監査人に提出する証憑として、顧客への評価版納品メールに本来記載されていなかったバージョン番号を追記したり、送信日時を変更するなどの改変が行われていました。
これらの結果、2015年12月期以降、費用が過少計上され、資産が過大計上される状況が継続していました。特別調査委員会は、適切な資産化範囲を再検討し、過年度の会計処理を訂正する必要があると結論付けています。
発生原因の分析
事業環境と背景
ACCESSは2017年1月期以降、ネットワーク事業・OcNOSを次の成長ドライバーとして注力するようになりました。同社は2001年の上場後、2010年1月期には売上高約320億円まで成長しましたが、その後縮小傾向となり、2017年1月期には約66億円まで減少していました。
このような状況下で、IPI社のOcNOSに期待が集まり、積極的な投資が行われました。
また、特殊な株主構成として、2012年頃からAl社による株式取得が進められ、2019年には44.13%を保有するに至りました。この影響で、ACCESSは継続的に株価向上を求められる状況にありました。
動機・プレッシャー
調査対象者のXd氏、Xc氏、Xe氏らは不正の認識を否定していますが、客観的事実関係と整合しない供述が多く見られました。2017年1月期以降、ネットワーク事業への期待が高まる中で、これらの幹部は予算達成に対する恒常的なプレッシャーを感じていたことが推認されます。
特に2019年1月期の東証市場第一部への市場変更に向けて、予算を着実に達成することが重要な課題として認識されており、このプレッシャーが会計不正の動機につながったと考えられます。
内部統制の問題
IPI社における内部統制には深刻な問題がありました。管理機能がCFOであるXe氏に集中しており、相互牽制が機能していませんでした。契約書管理、取引先管理、出荷管理、売掛金回収管理など、各業務フローが杜撰な状況にありました。
さらに、ACCESSからのコントロールも不足していました。IPI社は高い独立性を有しており、ACCESSにはネットワーク事業を実質的に所管する部署が存在せず、過去からXb氏やXd氏が兼任する形で管理されていました。
意識・組織風土の問題
マネジメント層における規範意識の欠如が深刻でした。Xc氏、Xe氏、Xd氏らは、ACCESSの社内承認プロセスの無視、監査人への情報隠蔽、証憑の改変など、組織的な隠蔽工作を行っていました。
また、IPI社全体では日本の上場企業グループの一員という意識が低く、非上場企業的な体質が見られました。ACCESSによる買収から20年近く経つにもかかわらず、十分な統合が図られていませんでした。
ACCESS経営陣の問題
ACCESSの経営陣であるXb氏、Xd氏、Xc氏は、財務報告に関する意識や感度が低く、上場企業グループのマネジメントとして最低限必要な知見やインテグリティを欠いていました。さらに、本調査開始後にデータを消去するなど、不適切な行動も見られました。
この背景には、人的リソースの制約がある中で、継続的・体系的な研修が実施されていなかったことも影響していると考えられます。
これらの複合的な要因により、長期間にわたる組織的な会計不正が発生しました。事業環境の変化、株主からのプレッシャー、内部統制の不備、規範意識の欠如などが相互に作用し、不正を生み出す土壌を形成していたと考えられます。
不正のトライアングル
不正のトライアングルとは、米国の犯罪学者ドナルド・クレッシーが提唱した理論で、不正が発生する3つの要因「動機・プレッシャー」「機会」「正当化」を示したものです。この3要因が揃うことで、不正が起こる可能性が高まるとされています。
今回のACCESSの調査報告書で認められたXc氏、Xd氏、Xe氏等の調査対象者の不適切行為を不正のトライアングルに当てはめるとしたら、次のように考えられます。
動機・プレッシャー
- 業績目標の達成プレッシャー:売上高や利益目標を達成するため、赤字を避ける必要があった
- 株価・市場評価の維持:上場企業として投資家や市場の期待に応えるため、短期的な業績改善が求められていた
- 経営層の評価や地位の維持:自身の役職や報酬、経営上の影響力を守るため
機会
- 内部統制の不備:会計処理や売上計上に関する監視・承認プロセスが形式的で、実質的なチェック機能が弱かった
- 権限の集中:特定の経営陣が財務数値や取引内容の決定に強い影響力を持ち、牽制が効かない状況
- 監査や社内牽制の機能不全:取締役会や監査部門が、経営陣の会計処理に十分な疑義を呈していなかった
正当化
- 「一時的な処理」だとの認識:将来の業績改善で調整すれば問題ない、との自己正当化
- 「会社のため」という意識:赤字を避けることで会社や従業員を守ることになるという誤った認識
- 慣行や過去事例の存在:過去にも同様の処理が行われており、それを踏襲することが正当と感じた可能性